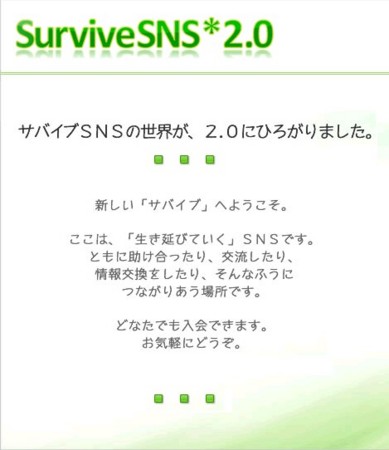物語が溢れてくる
秋山瑞人は危険だ。
彼の著書を「ライトノベル」という括りに閉じこめるには、あまりに危険すぎる。
彼の作品がライトノベルの代表作だって?なら、ライトノベルは危険だ。
かつてSFが、子ども向け空想小説から危険な先鋭思想を著すものに変わっていったように、ライトノベルもその羊の皮の下には、狼の姿を隠しているのかも知れないね。
【書評】
夢とは、かくも手前勝手なものだ……。
そうだな、その通りだ……。
夢というのは、そいつがどんな話の中に生きているか、ということだと思う。
誰でも、子供のころからいろいろな話を聞く。勇敢な猫が恐ろしい怪物を退治する話とか、醜い怪物が美しい牝猫に恋をする話とか。作り話ばっかりじゃない。戦で手柄を立てた兵の話とか、一生を貧乏人や病人のために捧げた坊さんの話とか……。そんな大層な話でなくてもいい。近所の何とかって猫は随分な男前だとか、うちのじいさんはネズミ取りの達人だったとか、知り合いが盗賊にやられて一族全員首を切られた、なんて話でもいい。なんでもいいのだ。
猫は、話がなくては生きていけないのだと思う。
猫は、子供のころから話を色々聞いて、最初のうちはただ、面白がって憧れたり驚いたり妬んだり哀れんだりする。そのうちに、猫は自分でも話を作れるようになって、今度は自分自身の話を作り始める。
これが、夢だと思う。
おれは行く行くは、こういう奴になりたいとか。
おれは将来、あそこに行ってみたいとか。
おれはこういう奴なんだから、こんなことはしないとか、してもいいとか。
そういう話がなければ、猫は一歩も前に進めないのだと思う。一息の呼吸もすることは出来ないのだと思う。
誰もが自分の話の中では王様で、しかも話の力というのは強力だ。言霊(ことだま)というやつだ。そいつを本当にすごい奴にしたりもするし、どうしようもない奴にしたりする。猫は、自分の話が要求するなら、自分の望むように自分の話を完結させるためなら、死ぬことさえできる。
ただ、
自分の話は、自分だけのものだ。みんなそれぞれ別々の、「自分の話」を持っている。
なのに、それぞれの「自分の話」は溢れ出す。溢れない奴もいるが、強力な話を持っている奴は、必ずそれを溢れさせると言っていい。そのうちにみんなこう言い出すのだ。おれの話では、お前はそんなことはしないということになっている。
おれの話では、みんなはこういうことをしてくれるはずだ。
そしてケンカが始まる。そのうちに戦が始まって、最期には葬式が始まるのだ。
……猫は昔から、そんなことばっかりしてきた。
そいつが生きている夢の中から、その猫を救い出すことは、たぶん、誰にもできないのだ。
それは「いい」でも「悪い」でもない、「悲しいこと」なのだと思う。
過去に、そういう奴がいたからこそできたことも、そういう奴がいたからこそ行けた場所も、たくさんあったはずだから。
過去にそういう奴がいたせいでできなくなってしまったことも、そういう奴がいたせいで行けなくなってしまった場所も、たくさんあったはずだから。
おれの夢は溢れていた。
……おれも、どうすればいいのかわからなかったんだ。
(p.242-244)
どれだけすごいんだよ。
ぼくは、この一節を、様々な場面で、何度も何度も思い出した。
物語は、必要で、危険で、暴力的で、魅力的だ。
それ無しでは生きていけないけれど、それは他人を巻き込み、争いを起こし、人の一生を台無しにしたりする。
物語は、危険だ。